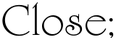

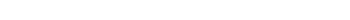
冬の夕暮れが寂しく部屋を橙に染め上げる。 あたしは知らない外国の街が印刷された葉書を眺める。 葉書を裏表と見やりながら遠い昔に思いを馳せた。 頭の中のフィルムがカタカタと廻る。 今この時と同じように、冬の夕暮れに染まった高校の学び舎が脳内に蘇る。 二つ年上の彼女に出逢った時、あたしの世界は変わった。 それ以来、鐘の音が鳴りクラスメイトたちが散ってゆけば、あたしは彼女 がいる教室へ走る。彼女と一緒に居たい。それだけだった。 話す時、彼女の長くて綺麗な黒髪は、はらりと揺れる。 シンと静まりかえった教室で彼女の優しい音だけが響く。 変わらない、変わることのないその日常が、愛おしかった。 「だけど、それじゃあ何もできないじゃない」 「わかってるよ。でも、どうすればいいか知らないんだもん」 「仕様の無い人間ね、美耶は」 「楽しければいいって言う考えはやっぱり駄目かな」 あたしは自分の茶色く痛んだ髪の毛をもてあそぶ。脱色しまくったせいで ぱさぱさごわごわしているあたしの可哀想な髪は向かいにいる人の髪とは 大違い。ごめんね、可哀想なあたしの髪の毛。 「美耶」 「なぁに?」 枝毛が妙に気になり、話を聞きながらあたしは枝毛を切ることに意識を 傾け始めていた。それに気付いたのか、彼女は真面目な口調になる。 思わず手を止め、彼女を見上げる。 「後悔しない人生を選びなさい」 「・・・・・・」 「なにをやってもいい。失敗したって良い。 だけどね、後悔はしちゃいけないわ」 「・・・・・・うん」 「本当に、本当にね。今はこの時だけなのよ。 この瞬間を逃したら、何もなくなっちゃうのよ」 そうして彼女は微笑んだ。 あの頃も今も、あたしにはどうして彼女があんな事をあのような 酷く悲しそうな顔をして言ったのか解らない。ただ、只管に 彼女の表情が脳裏から離れない。 あんなに切なく苦しげな表情を浮かべて微笑みかけてくれる人を あたしは知らなかった。 彼女の黒髪が夕日を浴び、薄らと橙に染まる。白い頬も橙に染まる。 けれども、彼女の黒い黒い瞳は永遠に黒いままだった。 透き通るような黒さ。 そのまま吸い込まれてしまいたくなるほどの黒さ。 今でも鮮明に思い出される。 あの時、あたしは彼女に対し恋に落ちていたのかもしれない。正しくは 恋愛感情なんて俗っぽいものなんかじゃなくて、もっともっと大切な感情。 だけど分かりやすく言うならば、それはまさしく恋だった。 狂おしいほどに愛しくて、切なさで死んでしまいそうになるくらい 欲していた。 |