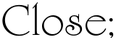
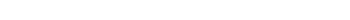
今なら分かるかもしれない。どうしてあの時、あの二人を見るのが 嫌だったのか。 彼は、彼女にとても近い空気を持っていた。あたしが欲しているのに、 決してなれないポジション。 彼女の相談者であり絶対の理解者。そこに彼はいた。 彼と一緒にいると彼女は微笑む。黒い瞳をゆるめ、薄い唇に華を咲かせる。 安心したような表情。 あたしの中で彼女はとてもとても大事な人だった。触れてはいけない聖域。 彼女はそこに存在していた。 存在していなくてはならなかった。 けれども、あの日あの時の彼女は、あたしの彼女ではなかった。 ただの「人」に成り下がってしまった彼女。神聖である筈の人が、ただの 人になってしまったのが酷く腹ただしかったのだ。 もっと言えば、それをあの喰えない笑みを浮かべる男がそうさせたという 事実が憎らしかった。 幼稚さ故のエゴイズム。 そしてそれ以来、大好きで大切だった彼女とどう接すればいいのか全く分ら なくなってしまった。 まるで闇夜の中、灯台を見つけられない船のように、母親を失った子供の ように、あたしは進むべき方向が分からず彷徨ってしまっていた。 彼女は何事もなく接してくるがあたしは、何をどうすればいいのか全くもって 分からなくなってしまっていたので、愛すべき彼女が目の前にいても、金魚の ように口をパクパクするだけで何も話せなくなっていた。 そんなあたしを見て、彼女はあたしを馬鹿にすることなく変わらぬ美しい笑顔 で見つめてくれていた。 それがまた、あたしを惑わした。 お世辞にも精度の良くない脳は混乱を起こす。 今、目の前に存在する彼女は、嘗てあたしの聖域に存在していた彼女では ない。ただの人になってしまった。 それなのに、彼女の笑顔はやさしくあたしを包み、あたしは其の事にどう しようもない切なさを覚える。 理由なんて分からない。 ただもう、認識と現状のギャップにあたしの脳は容量オーヴァーを起こし、 処理しきれない感情と意識がパンクして、思考回路が停止する。 そうして再び、金魚のように口をパクパクパクパクさせてしまうのだ。 だからあたしは距離を置いた。 「もうすぐ受験だから」なんて、時期が早すぎて不自然にしか聞こえない 言い訳を彼女に突きつけて、離れた。 惨めなあたしを彼女に見せたくない。もっと言えば、彼女の隣にいる 「賢治」に見られたくない。比べられたくない。 あたしがつまらない人間なんだってことを悟られたくなかった。 嫌われることを何よりも恐れた。 彼女に嫌われたらあたしは死んでしまう。体裁なんて何も考えない。 只もう、赤子のように泣き喚いて「見捨てないで」って醜く縋り付くだろう。 そんな別れ方はご免だった。 彼女と共有することのできない時間は思っていた以上に空虚で退屈。 只管、受動的に全てをこなした。 只管、日々が過ぎ去るのを待った。刺激がなんにもない。 自分から距離を置いてしまったため、あたしはどんなに寂しくて切なくても 彼女に頼ることができなかった。 夜中の二時過ぎに携帯を取り出し、メールを新規作成。 件名を打ち終えてから気付く。 ああ、あたしから離れたんぢゃない。 |