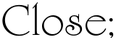
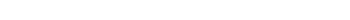
|
a short short story.
夏の夕暮れの空は、 青く明るいのに、切ない匂いがする。 自転車で土手を駆ける。 背の高い、草の匂いがする。 太陽の光を反射して、川面が光る。 息を切らして、坂道を駆けあがる。 西に落ちていく太陽がまぶしい。 「今日はどこいく?」
山か、川か。 振り返った彼は、瞳を細め、破顔すると気持ちのよい声で答えた。 「かわ!!」
彼は、町では見たことのない人間で、 きっと、珍しかったのだ。
子供特有の明け透けない考え方や反応はなく、
彼はとても落ち着いていた。 「なあ、生まれはどこなんだ」 「・・・生まれは、ここだよ」 「うっそだぁ。顔さ見たことねぇ」 「普段はここじゃないところに住んでいるから」 「都会?」 「・・・・・・そんな感じ」 「いいなぁ、都会」 「そんなことないよ」 「夏、終わったらまた都会に行くんか」 「たぶん」 「したら、また来年も遊べんな!」 「……ああ、そだな」
今思えば、あのときの彼はとても不思議な顔をしていた。 「来年、また・・・・・・」
ふとあの夏のことを思い出した。
そして、同じように陽を浴びていた筈なのに、
|